曹洞宗 青龍山 祇陀寺(ぎだじ)岩手県盛岡市大慈寺町
祇陀寺(ぎだじ)は大智禅師を開闢開山とする曹洞宗の寺院です。
寺だより
もうすぐお盆(盂蘭盆会-うらぼんえ)
もうすぐお盆です。盛岡では8月13日から16日がお盆です。日ごろ忙しく生活をしていますと、目先のことに追われ、ややもすると大切なものを見失いがちになります。心も生活と一緒に揺れ動いていますので、ひとの気持ちや物事が正しく写りません。こんな現代日本社会にも、昔から営まれている素晴らしい行事があります。それは極めて固有的な仏教儀礼であり、日本独特の伝統行事であるお盆です。
せっかくですから、親しくご先祖さまをお迎えし、生活のすべてを報恩感謝の実践期間にしてみてください。
お盆
お盆は、ご先祖さまの御霊(みたま)を供養するための行事とされていますが、仏教ではこの行事を「盂蘭盆会」(うらぼんえ)といいます。また「盆会」 「精霊会」 (しょうりょうえ) 「魂祭」(たままつり) 「歓喜会」などともよばれています。
その起源は古く、インドにはじまり、中国を経て、ご先祖さまのみならず生きとし生けるものすべてに供養を施し、幸福を願う行事として、わが国に伝えられ、今日まで受け継がれてきています。
お盆の時季は、一般に7月あるいは8月の13日~16日とされ、盛岡は8月です。
【目連伝説】
お盆の行事は、インドにはじまり、といいましたが、実際には仏教が中国に広がる間に起こったものであろうと考えられています。この盂蘭盆会の起源を説いた「盂蘭盆経」は中国で成立したお経であると考えられているからです。安居(百日間の修行)の終わった日に、人々が衆僧に飲食などの供養をした行事が転じて、祖先の霊を供養し、さらに餓鬼に施す行法(施餓鬼)となり、それに儒教の考の倫理観が加わり、目連尊者の亡母の救いのための衆僧供養という伝説が付加されたものと思われます。
盂蘭盆経に説かれているのは次のような話です。
安居の最中、神通第一の目連尊者が亡くなった母親の姿を天眼通(一切の世界を見通せる力)を使って探すと、餓鬼道に堕ちているのを見つけました。喉をからし飢えていましたので、水や食べ物を差し出しましたが、ことごとく口に入る直前に炎となって、母親の口には入りませんでした。目連尊者は大いに悲しみ、お釈迦さまに救いを求めたところ、六つの神通力を得たような目連尊者でも、ひとりの力では亡き母を救うことはできない。しかし十方の修行をしている者たちの力が集まれば、その苦しみを解き放つことができるだろうとおっしゃったとされています。また、夏の安居の終わった自恣(じし)の日(7月15日)に、供物を供え、十方の仏や僧に供養することにより、亡き母だけでなく七世の父母に至るまで苦しみから解き放たれるであろうとも説いています。
【お迎え】
ご先祖さまの御霊をお迎えするには、まず盆棚(盆飾りのこと)をつくります。盆棚は呼び名も形も様々です。盆棚をつくらないところでは、お仏壇を飾ってご先祖さまの御霊をお迎えいたします。
またお盆には、家族そろってお墓を掃除し、お花を飾り、お参りをしたいものです。
13日の夕方から夜にかけてはお墓や家の玄関先などでご先祖さまの御霊をお迎えするために「迎え火」を焚きます。
【お送り】
お盆中、大切におもてなしをしたご先祖さまの御霊は、15日の夕方、あるいは16日の午前中にお送りします。
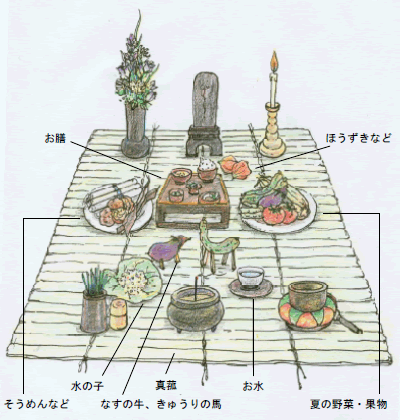
【精霊棚の飾り方(一例)】
まごころの精霊棚
私たちの先人は、ご先祖さまに対する温かいまごころを精霊棚にも形にして伝えてくれています。
真菰(まこも)や芦で編んだ敷物は、お迎えするご先祖さまが少しでも涼しいように、快適に過ごしていただけますようにという心遣いでしょう。また、お迎えするときは足の速い馬で来ていただき、お送りするときはゆっくり歩む牛でお帰りいただきたいということから、きゅうりの馬となすの牛を用意します。これは少しでも長い時間をご先祖さまと共有したいという想いからなのでしょう。
(水の子:洗米と、なすときゅうりをさいの目に切ってまぜ、蓮の葉やお皿に盛ったもの)